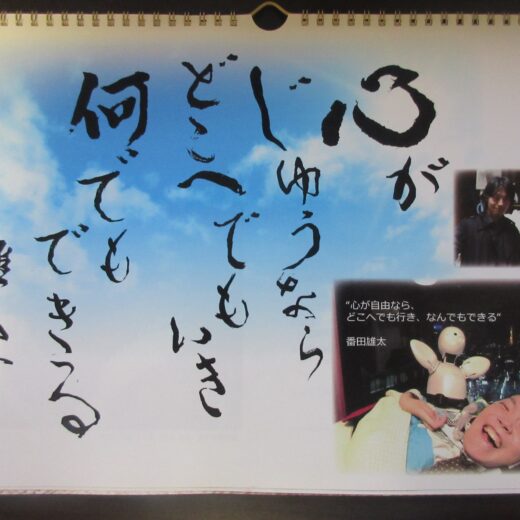空海が活躍した頃の中国は、唐王朝が支配していました。
当時、最先端であった密教を日本に持ち帰ったのが、空海の大きな功績です。
彼のすごいところは、仏教だけでなく、そのほかのジャンルについても
最先端のものを持ち帰ったところでしょう。
それは「書」にも及びました。
中国では王羲之という人の書をお手本にして書を習う伝統がありました。
写真を見てください。

空海の「風」と王羲之の「風」です。
そっくりでしょう。
ここから空海も王羲之の書をずいぶん学んでいたのがわかります。
空海が唐に滞在していたころには、王羲之もさることながら、
顔真卿という人の書法が最先端として流行していました。
丸太のような力強い線が特徴です。
空海はこの顔真卿の書法をいち早く自分の書に取り入れました。
おそらく日本人では空海が初なのではないでしょうか。
同時期に遣唐使だった最澄には、王羲之書法が見られますが、
顔真卿の書法は見られません。
最澄は1年だけの短期留学だったため、
密教もそのすべてを持ち帰れなかったし、
書法も満足に持ち帰ることができなかったのでしょう。
結局、空海から学ぶことになります。
最澄は空海の帰国後、空海から密教を伝授されるわけですが、
なにせもともと年齢もキャリアも最澄の方が上だったわけですから、
腹の底ではおもしろくなかったかもしれません。
「風信雲書」ではじまる、国宝「風信帖」は、空海が最澄の手紙に返信したものです。
内容は、最澄の
「空海さん、比叡山に一度来てくれませんか?仏教の議論などしたいのです」という手紙に対し、
空海が
「今は忙しいので無理です。最澄さんがこちらに来てくれませんか?」
このように答えています。
この後、両者の仲は次第に険悪になっていったといいます。
真偽は定かではありませんが、仏教への見解の違いや弟子を奪われたなど、
いろいろあったといわれていますね。
風信帖は、「風」という文字からはじまりますね。
最澄を最上級に敬い、また空海はへりくだった表現がされています。
ただ、これは表向きには、、、だったと読めます。
どういうことか。
空海は、「書は形を万類に象るべし」
と説きました。
つまり、「文字というものは、自然界のあらゆるものの形をまねている」
と言っています。
で、風信帖の書き出しに「風」を持ってきています。
「風」という字は、もとは鳳凰の「鳳」の意味で、非常に大きな鳥が空を飛び、
その羽の音であり、羽の風が生み出すモンスーンなのです。
気象衛星からみた台風の中心には目がありますが、
竜巻にしても台風にしても、うごめく風の中心は目にみえて、
なにか大きな生き物のように見えます。古代の人間はそこに神の威力を見たわけです。
風の神は東西南北の四方別々にいて、その地域全体に神意を伝達しました。
そういう神話的な背景がある文字なので、漢字はさまざまな派生語が生まれていきます。
英語であれば、「風」は「wind」1つだけです。
window がありますが、その1つくらいしかありません。
時代とともに「鳳」の中から「鳥」がいなくなるように変化します。
代わりに「虫」が入りました。
この虫は、ただの虫ではありません。
実は「龍」なのです。龍の形を虫で表したんですね。
大空に棲むけものとは、龍なわけでして、風という字は、
龍が大空を駆け回る様を表している字なのです。
空海もおそらくこのことを知っていた。
知っていなくてもイメージで感じ取っていたのでしょう。
最澄に書く手紙の書き出しに「風」を持ってきて、
なにか宇宙の力というか、威力を発動させようとしたのではないかと考えられます。
で、ここからは私の勝手な解釈というか、説です。 笑
「風」を書く時に、2画目は、はねますよね。
ところが、空海はちょっと変なはね方をしている。
前述の王羲之の「風」は筆の流れにまかせるまま、
いたって素直にはねています。
空海の「風」を見てください、

はねの部分が止まっている状態で終わっています。
この書き方は、はねる前に筆をおそらく右回転に回してから
ゆっくりと筆を抜いていくという常識ではありえないような筆の使い方をしているんです。
これは私の勝手な解釈ですが、
おそらく空海は、この当時最先端の書の筆法を進化させた
自分の筆法を最澄に誇示したのではないかと思えます。
「俺はこんなことまでできるんだよ」という笑
それともう1つ。
空海は、なんらかの呪詛というか、法力のようなものを筆意に含ませたのではないかと思うのですね。
でなければ、このような不自然な筆遣いをする必要はない。
流れに任せてはねればいいものを、
なにか普通ではない「ねじれ」というか、こねくったなんともいえない氣のようなものをほうりこんでいる。
最澄の幸先を念じたものであると信じたいのですが、
その後の二人が険悪になったということを考えると、
もしかして・・・・と思ってしまいます。
人間・空海は「清廉さ」だけでは語れない、
魅力的な人物であったのだろうと、
この書から見えてきます。