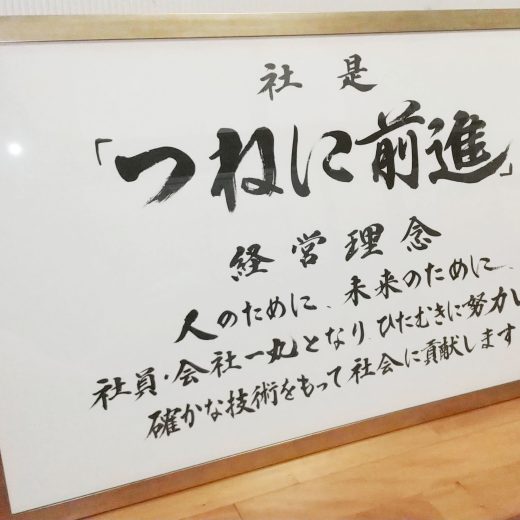こんにちは、書家の龍和です。
私は、企業の理念やビジョン、社是を筆で表現する
「毛筆理念」というコンテンツの日本ではじめての専門家として
活動を続けてきました。
この仕事をしていると、時々こう尋ねられます。
「企業理念を筆で書くというのは、昔からあった文化なんですか?」
答えは「はい、そして“今こそ必要な文化”です」と言いたいのです。
この記事では、毛筆で企業理念を書く文化がなぜ生まれ、
なぜ現代において価値を持ち続けるのか、
その“歴史と背景”をお話ししたいと思います。
目次
古来の“書”文化に根ざす日本の精神
日本において“書”は、ただの文字ではありませんでした。
仏教が伝来し、空海や最澄が書に精神性を込めていたように、
書はその人の「心を映すもの」とされてきました。
平安時代のかな書、江戸時代の寺子屋、明治以降の近代教育。
いつの時代も、
“文字を書く”ことには、
その時代の精神が込められていたのです。
そしてそれは、家庭や商家においても同様でした。
「家訓」「家是」「道義」といった言葉が、
掛け軸や額に書かれ、
柱に掲げられていたのをご存知の方もいるかもしれません。
商家や武家が大切にした「見える信念」
かつての日本では、商いの心得や生き方の指針を
“書”で掲げることが当たり前でした。
たとえば──
-
商家:「正直を貫け」「利は元にあり」
-
武家:「義を守れ」「忠誠第一」
こうした言葉が、墨で、筆で書かれ、掲げられていたのです。
なぜなら、「言葉は掲げてこそ意味がある」からです。
声だけでは消えてしまう。
紙に印刷しただけでは、心には届かない。
だからこそ、一筆一筆に“魂”を込めて、残す必要があったのです。
企業理念に“魂”を込める時代へ
現代に戻りましょう。
戦後、日本企業は高度経済成長の中で成長し、
「理念経営」という考え方が広まりました。
「我々はなぜこの事業をするのか」
「社会に何を提供したいのか」
「社員にどう在ってほしいのか」
これらを明文化した「経営理念」は、
企業の軸であり、社員への指針となりました。
しかし、その理念が
見えない場所にしまわれていたり、形式的に掲げられていたりするケースも多い
のが実情です。
そこに、私は問いかけたいのです。
「あなたの理念は、会社のどこに“息づいて”いますか?」
パソコンフォントでは伝わらないもの”がある
私はこれまで、さまざまな会社の理念を筆で書いてきました。
墨をする音。筆の入り。呼吸のリズム。
そこには、パソコンでは絶対に表現できない“気”の流れがあります。
プリントされた文字は、整ってはいますが、どこか冷たい。
フォントに“意思”はありません。
それに対して、毛筆理念には人の心と熱量が宿るのです。
デジタル全盛の時代にこそ、“本物”を
AI、クラウド、リモートワーク──あらゆるものが画面の中で完結する時代になりました。
しかし、そんな時代だからこそ、人は“本物”を求めています。
-
一筆入魂の理念
-
空間の重心としての書
-
哲学を目に見えるかたちにした一枚
毛筆で書かれた理念は、
会社の“場”を整え、“人”を引き寄せ、“志”を深める装置
なのです。
私自身の歩みとこの仕事の原点
私は幼少のころから書をはじめ、
生きていく過程で、
「人の本質を書く」
というテーマに向き合ってきました。
そしてある時、ある企業の経営者にこう言われたのです。
「理念を、あなたの書で掲げてみたい」
理念とは、経営者の魂そのもの。
その魂を書で表現する責任と重さに、
私の書家としての在り方が変わっていったのを、
今でも覚えています。
未来へ──この文化を“つなぐ”仕事として
私が毛筆理念に取り組むのは、ただの“文字仕事”ではないからです。
それは、日本の精神文化を現代に接続し、
未来に橋をかける行為だと信じているからです。
書とは、心を映す鏡であり、志を形にする手段です。
理念とは、企業の魂であり、社会との約束です。
その二つを結びつける「毛筆理念」という文化を、
私はこれからも書き継いでいきます。
ご相談はお気軽にどうぞ
もしあなたが、理念に“魂”を宿したいと感じておられるなら、
ぜひ一度、お問い合わせください。ご相談は無料です。