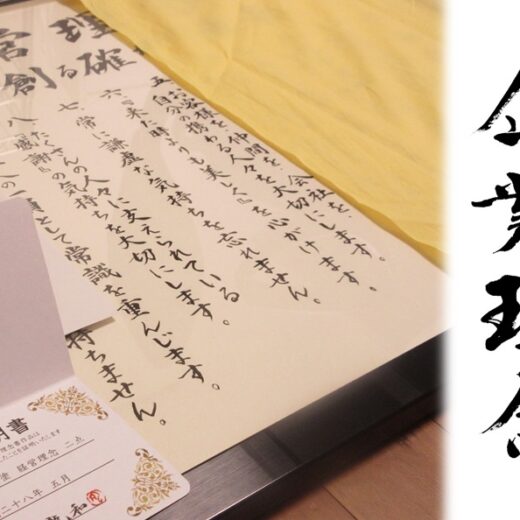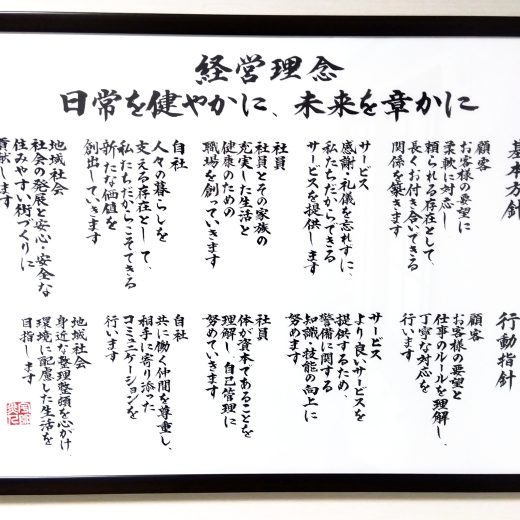墨は黒ですが、その黒も「七色の味わいがある」といわれます。
たとえば、青墨、茶墨など微妙な色加減のある深奥な世界です。
よい色の墨は水にこだわらなければなりません。
墨は固形墨といって、松の木を燃やした煤を、膠で固めたものを使用します。
硯で丁寧に磨るため、鮮やかな墨色の美しさを永い時間保つことができます。
源氏物語をはじめ、我が国の古文書が1000年以上経った今なお、
墨色をあざやかに保っているのは、この固形墨で書かれているからに他なりません。
さて、この固形墨を硯で磨りますが、
30ccの水を墨として使用できるまでに約30分かかります。
じっくり時間をかけて墨の成分である炭素が水に溶け、美しい墨色が産まれます。
この時、軟水であれば、より墨は磨りやすく、色も映えます。

江戸時代の画家、本阿弥光悦(1558~1637年)の有名なエピソードがあります。
徳川家康(1543~1616年)の御前でふすまの墨絵を描いたところ、
「水が良くない」といって筆を投げ捨ててしまいます。困ったのは家康の家臣たちです。
家康はさぞ立腹しただろうと顔色をうかがうと、「水を用意してやれ」と意外なコメント。
後日、仕切り直しとなり、家康が家臣に新しい水を用意させたところ、
光悦は「この水は良い」といって墨をすり、筆を執ります。
家康は初めに江戸の水、次に京都の水を用意させたと伝わります。
江戸の水は当時、硬水で、京都の水は軟水であったそうです。
書道家 龍和の提唱する【臨在(りんざい)主義(しゅぎ)】
書道家・龍和が墨をする際、水にこだわる理由は、
単に軟水であるから、ということだけではありません。
私たちは目には見えない世界への畏怖の念をもっています。
そして、それはなにかに宿るものであると考えます。
日本人は特にそのような意識が強いといわれています。
芸術にも、目には見えないけれど、なにものかが宿っている、(「宿る」=「臨在」)
このことを書道家・龍和は「臨在主義」と名付けています。
その宿っているものが次元の高い存在であれば、その芸術に触れるあらゆる生き物を、
きっと今より豊かな幸せへと導いてくださるー。
その芸術に触れるあらゆる生き物に幸せを運んできてくださるー。
そのような思いから、次元が高いとされる、パワースポットの水で墨をすっています。